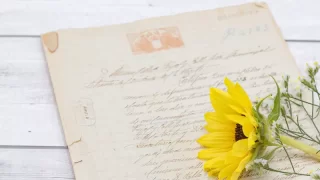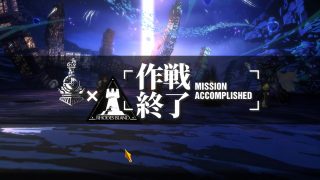一覧|教えてChatGPT!&格差の構造シリーズ
一覧|ゲーム(プレイ記録・攻略・考察・ビルドなど)
並び:記事更新順
スポンサーリンク
最近の動向(雑記アーカイブ)
-
本コンテンツ:その月、その日のつぶやきをまとめた記事です。下に行くほど日付が古くなります。
【つぶやき概要】12月1日|
 古田・通行人A・ふるる
古田・通行人A・ふるる
なんか気持ちがどっと疲れた気がするけど
それはそれとして、もしゼロからまたブログかなんか立ち上げるとしたら何やるんやろなとふと思った(やらんけど) 古田・通行人A・ふるる
古田・通行人A・ふるる
結局感覚的に突き詰めて積み上げたものを
人工的にやるのがマーケティングでブランディングちゃうんか(ブランデーちゃうで)