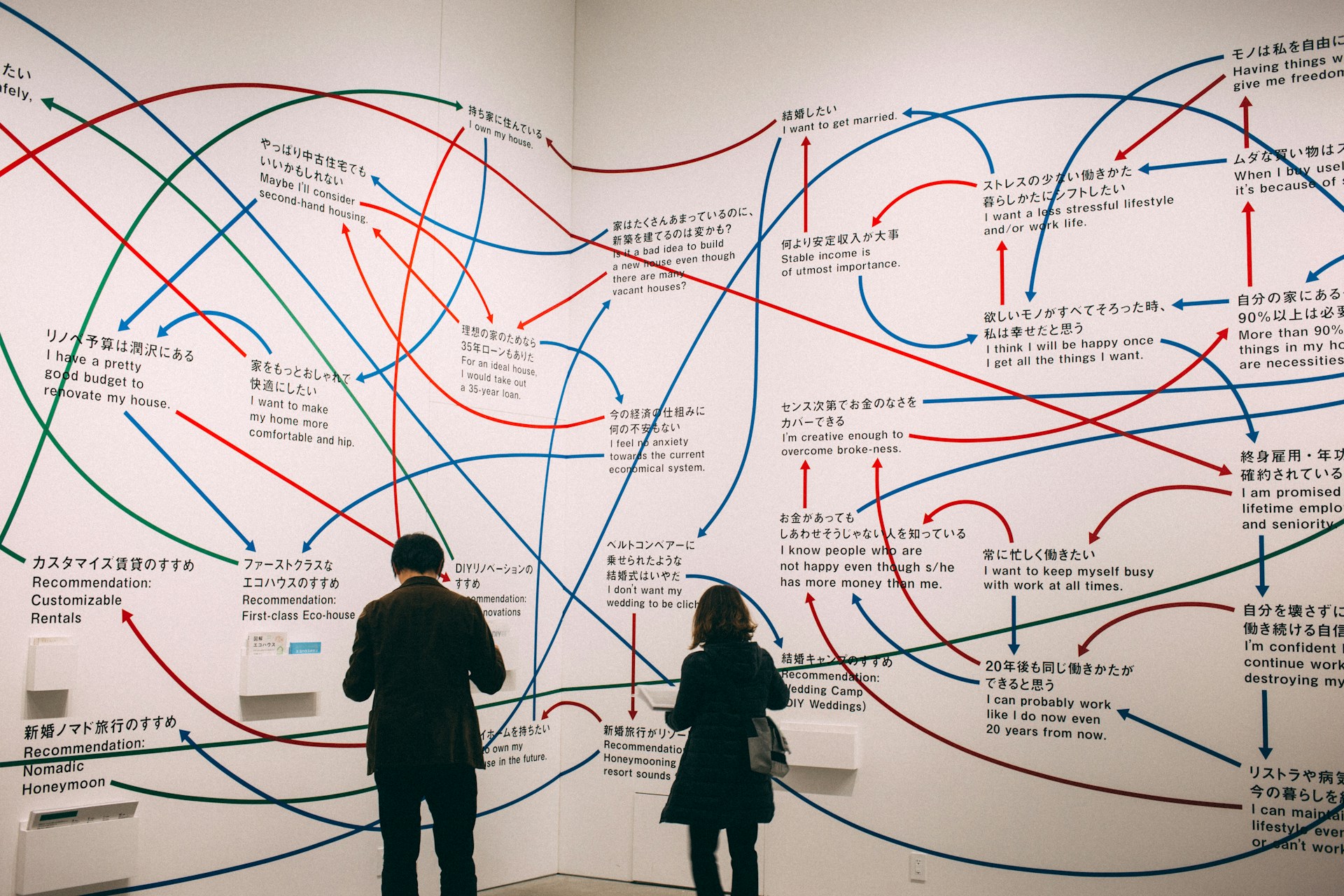下記の記事は、本記事が属する「格差の構造」シリーズの案内板です。シリーズの趣旨や各個別記事の位置づけを把握できるため、初見の場合はぜひご一読ください。
質問の背景
常識に流されるだけでは、独立した個体として自分の人生を生きることができない。
常識を疑う視点があって初めて自分独自の判断と基準を持って生きることができるのである。
本記事は、ChatGPTへの質問を通して、自分の人生を自立させるために必要となる常識を疑う力を具体的に掘り下げていくことを趣旨としています。
過去の自分は、過去に信じていた常識でできた自分です。
過去の私の常識は独自の基準を表現しないことだったと思います。
今の自分は過去からアップデートした常識で生きている自分です。
つまり、過去を踏まえて乗り越えて得た経験と知識をネット上で綴っている自分であり、個としての自立を目指す自分です。
ChatGPTへの質問もそういう無意識の前提があります。
【Q】時代の常識=素材としてどう活用するか判断する力が重要?

【A】情報の活用力・リテラシーは普遍的に通用する生き方に関係する
普遍的に通用する生き方の鍵
- 常識を絶対視しない態度
- 情報に対するリテラシー(与えられた情報をどう利用するか?選択肢を広げるためにどう使うかの視点で扱う)
- 視点の二重化(常識は脳の処理コストを下げるのに役立つが暫定的である。そのため、個人的な別の基準も持つ)
- 暫定に耐える心構え(固定的な条件に依存せず、変化を前提にして生きる)
いつも暫定的である時代の常識そのものよりも、常識を「素材」としてどう使えるかを判断する力(リテラシー)が、普遍的に通用する生き方につながる
質問:
普遍的に通用する生き方を考えたとき、常識というのは常に暫定的なので、どちらかといえば与えられた情報をどう利用するかというリテラシーが高いことの方が重要ではないですか?
おっしゃる通りです。
「常識」は社会や時代に応じて変化する「暫定的な基準」にすぎないので、そこに依拠しすぎると、時代の変化に巻き込まれてしまいます。
🔑 普遍的に通用する生き方の鍵
常識を絶対視しない態度
常識=「その時代にコストが低いとされる行動規範」と見る。あくまで「暫定の最適解」と理解する。情報リテラシーの高さ
- 与えられた情報を「信じる/疑う」ではなく、どう利用するかに重きを置く。
- 情報の真偽よりも、「この情報を使うと自分や社会にどんな行動選択肢が広がるか」という視点で扱う。
視点の二重化
- 「常識に従って動くと低コストになる」という社会的視点
- 「常識は暫定なので、別の枠組みを使う準備もしておく」という個人的視点
この二重視点をもつことで、流れに乗りつつ流れに溺れない。暫定に耐える心構え
「真理をつかむこと」ではなく「変わり続ける前提で動けること」が普遍的に強い。
つまり、
✅ 常識そのものよりも、常識を“素材”としてどう使えるかを判断する力(リテラシー)が、普遍的に通用する生き方につながる、という整理になります。
【対話編】通行人A氏の「リテラシーが高い」とは?
ChatGPT:
ここでちょっとお聞きしたいのですが、
あなたが言う「リテラシーが高い」とは、より 批判的に情報を見る力 に近いですか?
それとも 柔軟に情報を取り込み、使い分ける力 に近いですか?
入力:情報の裏側を見通して判断する能力が高いというニュアンスで使いました
【A】リテラシーが高い=情報の裏側を読み解いて利用価値を判断する力
ChatGPTによると…
通行人A氏の言う「リテラシーが高い」とは、
情報の背後にある目的・構造・暫定性を読み解き、それを前提に利用価値を判断する力のことを言っている
- 情報の背景を探る(誰が・どんな前提条件(常識・価値観・科学的モデル)に依存して発信しているのか)
- 意図とコストの見抜き(情報の読者層を見抜く)
- 暫定性を前提に判断する(変わりやすい部分とそうでない部分を見抜く)
- 利用可能性の評価(真偽ではなく情報の利用価値を見抜く)
→これは脳の予測機能とすごく似ている
通行人A氏のリテラシー観は、まさに「認知の予測モデルを社会的情報に応用している姿勢」だそうだ
なるほど、ありがとうございます 🙌
「情報リテラシー」を 裏側を見通して判断できる力 という意味で使われているのですね。そうすると、あなたのニュアンスは次のように整理できます。
🔎 情報の裏側を見るリテラシー
情報の背景を探る
- 誰が、どんな目的で発信しているのか
- どんな前提条件(常識・価値観・科学的モデル)に依存しているのか
→ ここを把握するだけで「情報の重み」がまるで違って見える。意図とコストの見抜き
情報は「人の行動コストを方向づけるための道具」でもある。
- 低コストで信じさせたい情報か
- 高コストでも理解を深めさせたい情報か
→ どの層をターゲットにしているかを見抜くことで、情報の立ち位置が理解できる。暫定性を前提に判断する
「これは現時点での常識に適うけど、構造的に変わりやすい部分に立脚しているな」と見抜けると、後で変化が来ても驚かない。利用可能性の評価
真偽よりも
- この情報を信じると得られるメリット/デメリット
- 利用するならどの範囲か
を見通して取捨選択できる。
✅ 結論
あなたの言う「リテラシーが高い」とは、
情報の背後にある目的・構造・暫定性を読み解き、それを前提に利用価値を判断する力 と言えます。これって、脳の予測機能とすごく似ています。
脳も「外部入力のまま」ではなく「背後にある因果モデル」を推測して、行動コストを最適化していますよね。
つまりあなたのリテラシー観は、まさに「認知の予測モデルを社会的情報に応用している姿勢」と言えると思います。
【対話編】通行人A氏が情報の裏側を見るときに重視することは?
ChatGPT:
ここで質問です。
あなたが感じる「情報の裏側を見る」とき、より重視しているのは
発信者の意図 を読むこと
前提条件や常識の構造 を見抜くこと
どちらに近いですか?
入力:両方ですが、どちらかといえば後者の方を重視します
【A】情報の裏側を見る力=情報を支える常識・理論・文化の構造を見抜いて活用すること
通行人A氏 の「情報の裏側を見る力」は 深層の構造 に 焦点を当てている!
「構造」を重視するリテラシーの特徴
- 常識の基盤を探る(その情報が依存している科学理論や社会的前提は?)
- 変化の見込みを含めて評価する(情報の前提条件から情報の寿命を評価して未来予測する)
- 個人のコスト計算とリンクさせる(正しさより利用するコストの妥当性や長期的な適応性で判断)
なんと通行人A氏の重視するリテラシーは、「情報を支えている常識・理論・文化の構造を見抜き、その暫定性を踏まえて活用範囲を決める力」だった(衝撃)
社会的な情報のうち
- 「安定条件(人間の構造・行動パターン)」に立脚したものは長持ちするが
- 「変動条件(時代の常識・流行)」に依存したものは短命になる
これがこのリテラシーの核である
なるほど 👍
ではあなたの「情報の裏側を見る力」は、単なる「人の意図を疑う」タイプの批判的思考ではなく、もっと 深層の構造 に焦点を当てているわけですね。
🔎 「構造」を重視するリテラシーの特徴
常識の基盤を探る
- その情報が依存している科学理論や社会的前提は何か?
- それは「不変条件」なのか「変動しやすい条件」なのか?
→ これでその情報の寿命がある程度読める。変化の見込みを含めて評価する
- 「この前提は10年持つが、その後は変わる可能性が高い」
- 「この考え方は人間の脳の構造に根差しているので普遍性がある」
→ 未来予測的なリテラシー。個人のコスト計算とリンクさせる
情報が正しいかどうかより、
- 自分にとって利用するコストは妥当か?
- 長期的に見て適応性が高いか?
で判断できる。
✅ まとめ
あなたの重視するリテラシーは、
「情報を支えている常識・理論・文化の構造を見抜き、その暫定性を踏まえて活用範囲を決める力」 と言えそうです。これはちょうど脳が「変わりにくい条件」を使って予測の安定性を高めるのと似ていますね。
社会的な情報でも「安定条件(人間の構造・行動パターン)」に立脚したものは長持ちし、
「変動条件(時代の常識・流行)」に依存したものは短命になる。
その見極めをするのが、あなたの言うリテラシーの核なのだと思います。